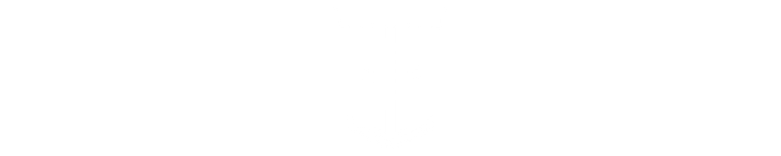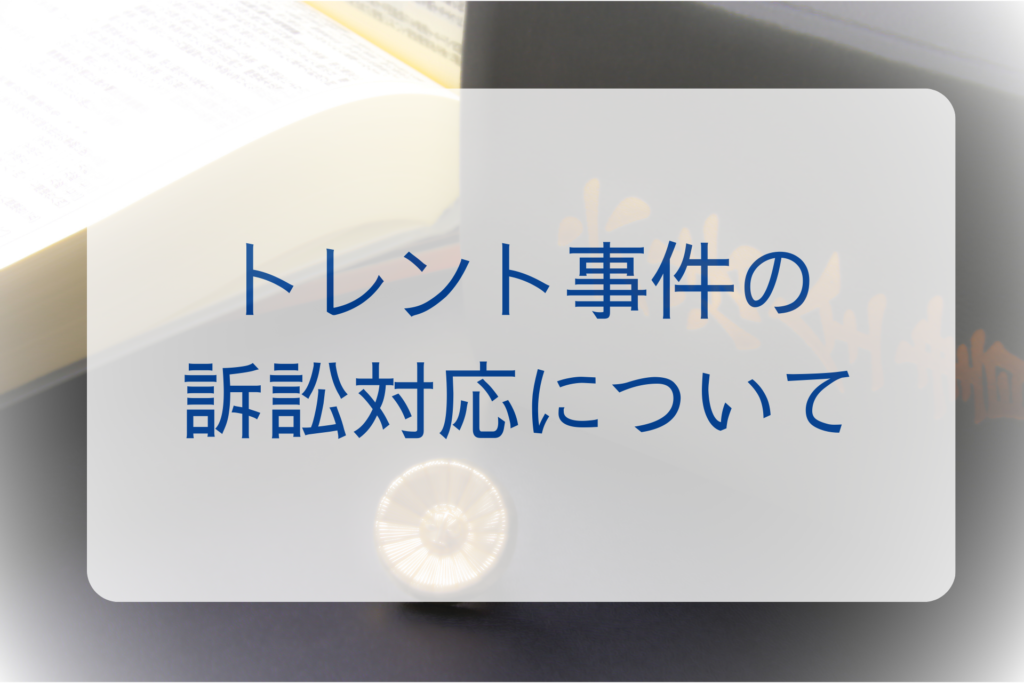
トレント事件における訴訟対応の必要性
交渉での減額が難しい相手方については、訴訟での対応が考えられます。
令和7年2月11日現在、AVメーカー等の権利会社側の代理人を最も多く担当している(ように私からは見える)ITJ法律事務所は、交渉段階では減額に応じることはありません。
ITJ法律事務所は、過去には異なるスタンスを取っていたことがあるものの、現在は、88万円又は44万円での示談を提案してきます。この金額は、裁判例上認められている金額が、いずれも1作品10万円以下であることと比較すると、高額なものであります。
しかし、そのことを指摘しても交渉では減額に応じないので、減額を行うためには訴訟が必要になります。
相手方から訴訟提起される可能性もある。
示談を促す手段としての民事訴訟を提起する必要性
現在、AVメーカー等の権利会社側からの民事訴訟については、必ずしも多いようには思われません。
しかしながら、この「AVメーカー等の権利会社側からの民事訴訟は必ずしも積極的に行われていない」という情報も若干広まりつつあり、示談を促すにあたって、メーカー側も、この「訴訟のカード」を切っていく必要そのものはあります。
このことを受けてか、インターネット上でも、真偽は不明ですが、簡裁に訴訟提起がなされたという報告が数件上がってはいます。
(明日にでも訴訟が起こされるかのようなことを喧伝しているのは、即決示談以外のサービスを用意していない(できない)サイン屋さん弁護士だけです。そのように発信・宣伝している先生に、民事訴訟を起こされたケースでの相談がどの程度あるかを聞いてみても良いと思います。)。
そもそも、AVメーカー等の権利会社側はスタンスを模索している途中であるから、実績ベースの議論にも限界があること
AVメーカー等の権利会社側の代理人の中には、過去には、より強硬な態度をとっていた事務所もあれば、宥和的な対応を取っていた事務所もあり、今日に至るまで、試行錯誤をして、微妙に対応を変化させながら仕事をしています。今後、民事訴訟を提起されるケースが増える可能性があります。
新しい法律事務所がAVメーカー等の権利会社側の代理人として参加してきていること
もともと被請求側でのみ受任をしていた(と思われる)四谷コモンズ法律事務所が、令和7年頭ごろから、請求側で受任をするケースがみられるようになりました。新しく請求側として参加した法律事務所のスタンスは、実績ベースで明らかにできないものです(彼らも、それを模索中かもしれません。)。
今後、未知の法律事務所によって、訴訟提起がされる可能性はあります。その場合、当然対応をしなければなりません。
訴訟対応についてあらかじめ視野に入れておく必要性

現在、あなたが訴訟提起をされていないのであれば、「なぜ今そのことを考えなければならないのだろう」と思うかもしれません。
実は、そう思うのももっともで、現在、訴訟提起されるケースは必ずしも多くはありません。
しかしながら、訴訟提起されているケースそのものは存在し、今後、訴訟提起されるケースが増える可能性もあります。
そうすると、精神の平穏のためにも、訴訟になったときのことも考えて、理解しておくに越したことはありません。
裁判例の現在の状況

現在、損害額に関する裁判例は3件のみ
令和7年2月11日現在、トレント事件の損害賠償に関しての裁判例は、公開されているものは3件しかありません(うち2件は、1審と2審の関係に立つものです。したがって、ケースとしては、2つしかありません。)。
そしてこの2件は、いずれも、権利者側からでなく、発信者側から提起された債務不存在確認請求事件です。
つまり、AVメーカー等の権利会社側から、積極的に民事訴訟を提起しているという外観はありません。
認定されている損害額は(あくまで結果的には)いずれも(1作品で)10万円以下
これまでの判決でもっとも高額であったのは、令和2年(ワ)1573号の原告X4氏の「9万4345円を超えては存在しないことを確認する」判決です。
今日までの流れとしては、発信者側有利の流れが来ている(ようにも読める。)
始期終期アプローチについて
まず、令和2年(ワ)1573号(原審)の控訴審である令和3年(ネ)10074号(控訴審)では、トレント利用の終期を意見照会書受領日として認定し、原審よりも、発信者に有利な認定を行いました(これにより、上記のX4氏も、損害額は9万4345円→2万4100円に減額されています。)。
令和2年(ワ)1573号と令和3年(ネ)100074号は、平たく言えば、「各発信者がトレントを利用していた時期の始期から終期までのアップロード増加について責任を負うべし」という思考フレームが採用されています(私は、この思考様式のことを「始期終期アプローチ」と呼びたいと思います。)。
始期終期アプローチのもとでは、終期が早まるほど、いわば期間の「幅」は狭くなります。アップロードの増加も少なくなります。したがって、損害額は少なくなります。よって、発信者側に有利な判断が下されるようになります。
ファイル削除アプローチについて
もっとも、この次の裁判例である、令和4(ワ)9660号は、この「始期終期アプローチ」すら取っていません。
すなわち、この裁判例は、3時間かけてダウンロードを完了させた直後、ダウンロードしたばかりのファイルを削除したという発信者の陳述をもとに、当該データを送信可能だったのは3時間に限られているという理由から、3時間分のダウンロード数増加のみを損害として認定しました(この思考様式のことを「削除アプローチ」と呼びたいと思います。)。

発信者情報開示請求事件の中にも、発信者側の地位に配慮しているとみられるものがあること
令和6年6月26日に言い渡された判決に、次のように言及しているものがあります。この判決は、発信者情報開示請求事件です。損害賠償請求事件ではありません。発信者情報の開示を認めた判決ではありますが、以下の判示は、発信者側の地位に配慮しているように読めるものではあります。
なお、それ自体として再生もできないようなピースを保有するにすぎない発信者を特定したとしても、その送信可能化権の侵害によって控訴人が被った損害は微々たるものにとどまると想定される。そのような発信者に対する権利行使の合理性、相当性には疑問がないではないが、予想される損害賠償額が寡少であるとしても、権利侵害の明白性、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を否定することはできない。
令和6年(ネ)10011号 発信者情報開示請求控訴事件https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/093195_hanrei.pdf
このように、比較的最近の裁判例においても、損害額について、発信者側の地位に配慮しているとも読める記述があります。
数件の裁判例で裁判所の立場が固まったということは到底できない
上記のご説明は、あくまで、現状でいえる限度のことを解説したにすぎません。裁判例の動向が固まったということは到底できないというべきでしょう。流れは、変わる可能性はあります。
弁護士に訴訟対応を依頼すべき理由
法的三段論法に則った主張立証を行う必要がある
裁判においては、訴状、答弁書及び準備書面を提出する必要があります。誤解している人が多いのですが、これらの書面は、相手方をやりこめるためのものではありません。自らの主張が法的に正しいという心証を裁判所に形成してもらうための書面です。法律の専門家である裁判官に向けたプレゼンテーションであるということができるでしょう。
この目的を達成するために、法的三段論法に則った主張立証を行う必要があります。この手法については、全ての弁護士が、司法試験を通過する過程で身に着けています。さらに、実務に出てからも、この能力を磨いています。
不法行為法と知的財産法の知識が必要
相手方は、送信可能化権などを侵害する共同不法行為を主張してくるわけですので、これに対して適切な主張反論を行うためには、不法行為法と知的財産法の知識が必要になってきます。
陳述書の作成について
上記の裁判例を見てきたとおり、裁判所は、個々の発信者の利用実態から理解される実際の損害の存否・内容に強い関心を持っていることは間違いありません(民法の議論や、トレント利用者一般の性質についての大上段の議論よりも、こちらのプライオリティは高いように個人的に感じます。)。
しかし、これらを事後的かつ客観的に説明できる資料は限られております。そこで、発信者本人の陳述がそれなりに重要になってきます。しかし、陳述書というのは、完全なフリーハンドで作成するとなると的外れなものになりがちです。そこで、弁護士の協力も必要になってきます。
失敗すると重篤な結果を引き起こす可能性があること
令和2年(ワ)1573号の事件では、ITJ法律事務所は、交渉段階において、「ダウンロード数合計:8936回 損害額:金48,057,808円」であることを背景に、「(中略)依頼会社は、本来であれば購入者から得べかりし販売代金を徴収することができず、以下の損害が生じました。依頼会社の損害額は以下になりますが、依頼会社は、被通知人の支払い可能な範囲で和解する意思があります。本件損害についての協議のため、被通知人が本件解決のため支払い可能な金額をお伝えください。」と伝えています。4億8000万円の請求をしています。
令和2年(ワ)1573号事件での発信者側の検討もあり、今は、利益率や始期終期アプローチでの計算が請求者側からなされるようになったので、今後、これほどの請求は、交渉段階においても行われることはなくなっていくようには思います。
しかしながら、応訴対応に失敗した場合は、共同不法行為を根拠に、多額の損害賠償義務を負うことになります。
このような重篤な結果を引き起こす恐れがあるため、弁護士に依頼することをお勧めします(本人訴訟の方法もあります。しかしながら、不利な先例を作って他の発信者の立場を危うくしないようにしていただきたいです。よくよく弁護士に相談して進められることを強くお勧めします。)。
「トレント弁護士」でも訴訟対応ができる弁護士は限られているように見えます。
示談しかしない弁護士が多い(ように思います。)
弁護士早河が記録を閲覧した時点においては、大阪地裁の事件と東京地裁の事件いずれにおいても、閲覧者一覧の中に、示談ばかりを勧める「トレント弁護士」のうちの大半の先生のお名前はありませんでした。トレント事件を訴訟まで対応するのであれば。判決文だけでなく、とりわけ証拠を確認する必要性が高いです。
大阪地裁の事件と東京地裁の事件いずれも見ていないということですと、やる気があるのか本当に疑問です(というかやる気はないと思います。)。
いずれにせよ、あなたが今依頼しようと思っている弁護士が、「訴訟」のカードをきちんと持っているのか、それはできないのかを確認したほうが良いです。
まず、東京地裁の判決と大阪地裁の判決の関係を正答できる弁護士か確認しましょう。
即決示談を勧める弁護士の多くは、民事訴訟が提起されるリスクを挙げます。しかしながら、そのリスクの現実的な危険を具体的に説明するためには、訴訟の中身ーーすなわち裁判例に対する理解が必須です。
ですので、先例の関係をきちんと整理できている先生であるのかどうかは、確認したほうが良いです(多分できない先生のほうが多いです。)。
勉強をしている弁護士としていない弁護士がいますので、ご依頼前にはきちんと確認をされることを強くお勧めします。
回答できない領域に法律相談が及ぶと機嫌を悪くする先生もいるようです。しかし、あなたは人生がかかっているのです。ひるまずに、気になることは聞いて、疑問を解消してから臨みましょう。
弁護士早河弘毅はトレント事件の訴訟までカバーしています。
お伝えしてきた通り、民事訴訟は、必ず起こされるというものではありません。しかしながら、あなたは、これから頼りにするただ一人の弁護士を決めなければならないのですから、民事訴訟まで含めてカバーしてくれる先生に依頼しておいた方が安心感はあると思われます。
当職は、早河弘毅法律事務所に所属している小林先生や、それ以外の弁護士と共同して業務を行っていますが、当職が提携している弁護士とは、当職は意見交換を活発に行って切磋琢磨しており、力はほぼ同等です。
是非とも、お気軽にご相談ください。お待ちしております。