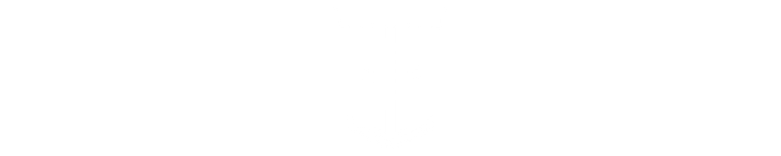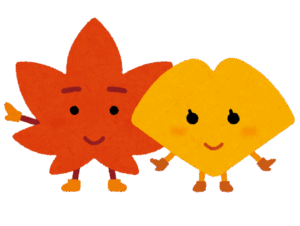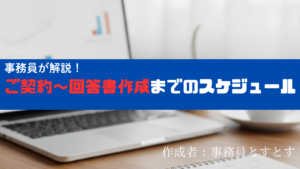「ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に関する注意喚起」総務省報道資料(令和7年11月7日付)について
概 要
解説動画を作りました。ファイル共有ソフトの利用はやめましょう。今後は刑事事件化するリスクは(以前よりは)高くなる可能性が(全く)ないとはいえないです(理由は動画を見ると分かりますが、資料を見ればより早く分かります。)。
動画
資料
動画を要約するとこうです。これは動画をAIに食わせて適当に出力しているわけじゃなくて、私が書いた文章をAIにパワポっぽくしてもらっているだけなので、読む価値はあると思います(動画見なくてもここ読むだけでも十分ですが、動画は応援してもらえるとやる気が出ます。)早河。
総務省報道資料
著作権侵害に関する注意喚起について
報道資料のポイント
開示請求の全体像
令和6年のプロバイダに対するアンケートでは15万件の開示請求があったと回答がありました。
※そのうち大半はテレサによるもの(具体的な割合は資料に記載なし)
ファイル共有ソフトの圧倒的割合
15万件のうち約14万件(95%程度)がファイル共有ソフトによる著作権侵害関係でした。
ファイル共有ソフトの種類
ファイル共有ソフトにはトレント以外にもCabos、Shareなども存在します。
※資料に明言はないが、「IPアドレスがすぐにわかる」との記載から、ほぼ全てがトレント(BitTorrent)関係と推測される
早河の感想
プロバイダーの負担への配慮
プロバイダーの負担が大きいことへの配慮が資料全体から見られます。これは資料冒頭で「発信者情報開示請求制度への支障」について言及されていることからも明らかです。
対権利者について
対権利者対応に対する言及がなく、示談金が高額であるとも述べていません。発信者側よりの発信でもなく、権利者側よりの発信でもないです。
現在の利用者の認識
現在ファイル共有ソフトを利用している者は違法アップロードの故意はないことがほとんどであると資料に明記されています。
今後の展開:故意認定の可能性
今後は、ファイル共有ソフトによる違法アップロードの存在が広く周知されることになります。これを知りつつファイル共有ソフトの利用を行っていた者については、故意が認定される可能性が出てきます。
資料の真の目的と副次的効果
資料の冒頭で「発信者情報開示請求制度への支障」について言及されていることから、プロバイダー(や裁判所)への配慮が第一にあると考えられます。
今後刑事化を活性化させるための発信というわけではないと思われますが…
副次的効果への懸念
このような副次的効果(故意認定による刑事事件化の可能性)が生じてもおかしくないように思われます。結果的に刑事化への道を開く可能性があります。